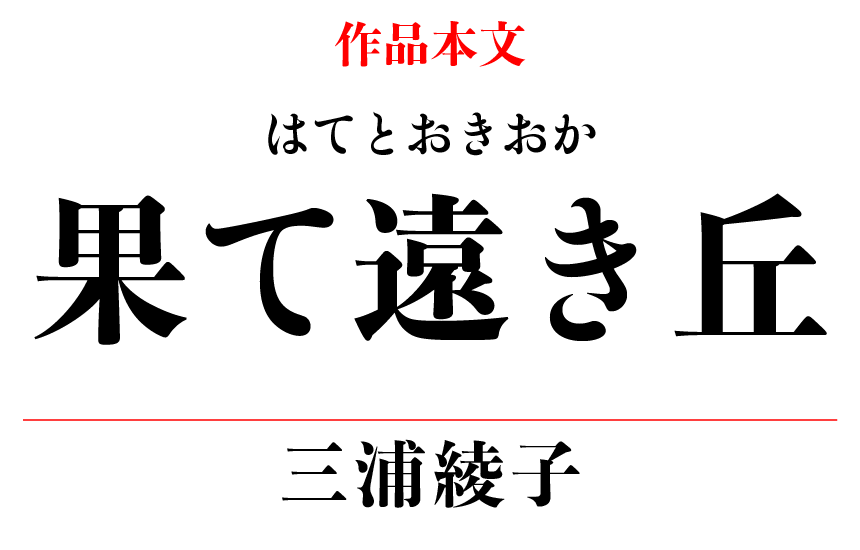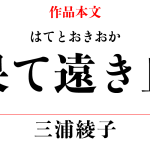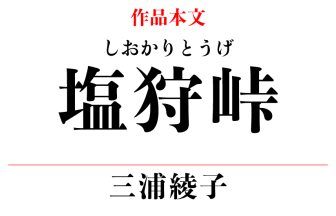恵理子は焼却炉のそばを離れたかったが、燃えつきるまでそばについているように、常々保子からいわれている。恵理子はぎこちなく焼却炉を見つめていた。煙が青くなびいて、川向こうの青年のほうに流れて行く。恵理子はかたくなに、青年のほうを見ようとしなかった。あの若い女性のうしろ姿が、恵理子をかたくなにしていた。紙屑が燃え終わるまで、青年に背を向けて、恵理子は立っていた。青年はギターを弾いていた。フォークソングのようだった。恵理子の知らない歌だった。紙屑が燃えつきたとき、恵理子は青年のほうを見、頭をさげた。青年は片手をあげた。昨日と同じだった。
〈作品本文の凡例〉https://www.miura-text.com/?p=2463