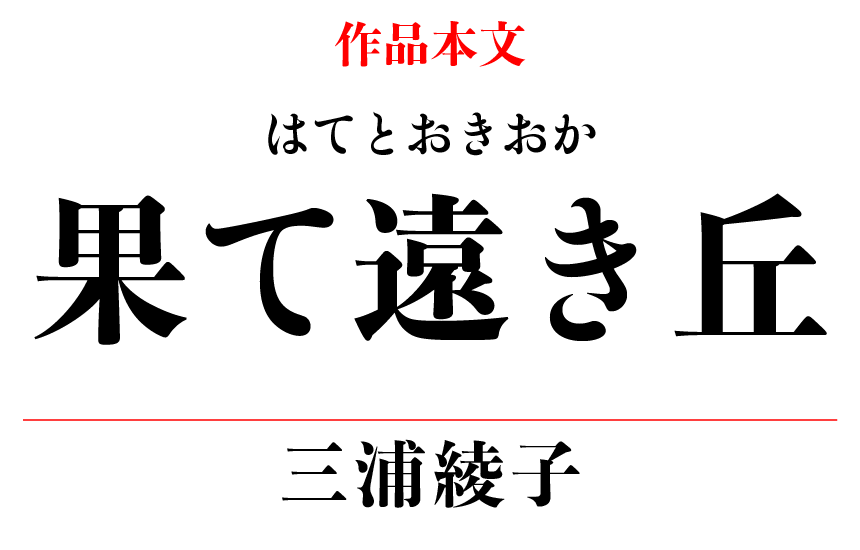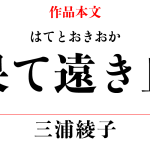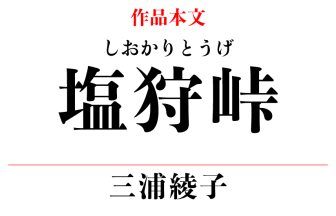たった一人の妹の名を、恵理子はそっと呼んでみる。あの青年と並んで、ぎこちなく茶席についていた香也子が、たまらなく愛しい。馴れた席でもないのに、あの席につらなったのは、どんなに必死の思いであったろうと、恵理子は胸が熱くなる。それは、あの時のくいいるような香也子の激しいまなざしが、何よりもそれを語っているような気がする。実の母と実の姉を、どんなにか慕ってやってきたのだろうと思う。これも、あれ以来くり返し恵理子の心にかかることだった。
〈作品本文の凡例〉https://www.miura-text.com/?p=2463