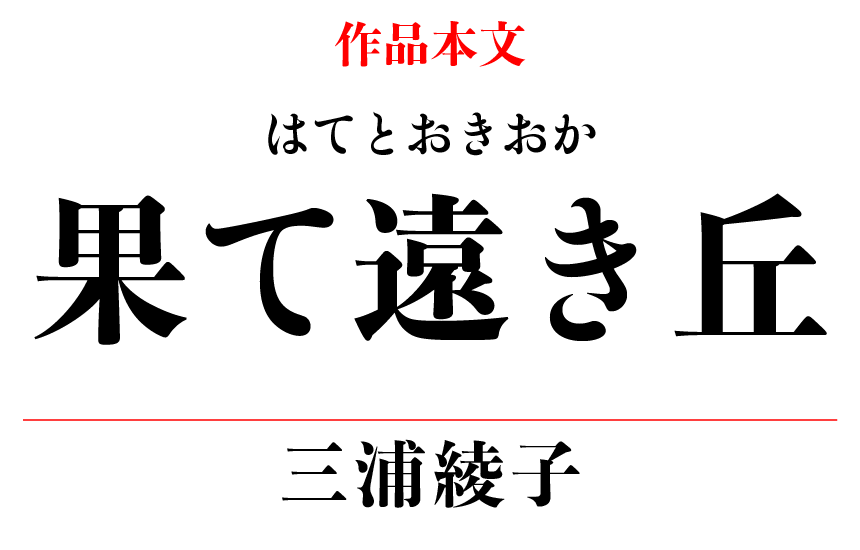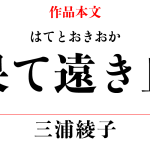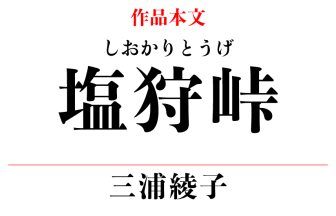保子は驚いて目をみはった。保子は旅行嫌いなのだ。外食さえ好まぬ保子が、誰が寝たかわからぬホテルのベッドに寝ることなどは、できないことだった。たとえシーツや襟布が新しかろうと、保子の神経は承知しなかった。一枚のシーツを通して、ベッドの汚れが、じかに身に伝わるような感覚を保子は持っている。どんな病気を持った者がそのベッドに寝たかわからないと、保子は想像するのだ。特に保子は、梅毒を恐れた。梅毒を持った者が、裸でベッドに寝たのではないかと恐れるのだ。
〈作品本文の凡例〉https://www.miura-text.com/?p=2463